犬の歯が黄ばむ原因とその対策、日常ケアについて|埼玉県志木市のアポロどうぶつ病院
志木市、さいたま市、朝霞市、新座市、富士見市の皆様こんにちは。埼玉県志木市のアポロ動物病院です。
今回は、犬の歯が黄ばむ原因とその対策、そして日常ケアのポイントについてお話しします。
歯の黄ばみは見た目だけでなく、健康にも影響を及ぼしていくことがありますので、しっかりとしたケアが大切です。
『黄ばみ』そのものは歯が黄色くなっているだけですので、口の中を見ることができればどなたでも気が付くことができます。
そのなかでも次のような症状には特に注意です。
◆とくに気をつけるべき症状
- 歯全体が黄色い
重度の歯石沈着か、『歯内出血』のうたがいがあります - 黄色い歯が何本もある
歯周病が進行して歯石が増えてしまっているか、『エナメル質形成不全』のうたがいがあります - 色がついているところが凹んでいる
『エナメル質形成不全』のうたがいがあります。 - まだ若いのに歯が黄色い
上と同じく『エナメル質形成不全』のうたがいか、体質的に歯周病が進みやすい可能性があります。」 - 歯の色がおかしくて、しかも形もおかしい
変形歯や外傷を受けた可能性があります。
このような症状が見られたら一度どうぶつ病院を受診することをご検討ください
👇👇👇
◆犬の歯が黄ばむ原因とは
犬の歯が黄ばむ原因として多く見られるのは、以下の3つです。
- 歯石の付着
- 色素沈着
- エナメル質の喪失
① 犬の歯石
歯垢が溜まっているところに、唾液中のカルシウムなどが作用すると、固まって歯石になります。
歯石は黄色から茶色をしていて、歯が黄ばんで見えますが、見分けるポイントとしては
・出っ張っている
・塊になっている
・凸凹がくっついている
のように見えることが多いです。
歯石は非常に硬く、ブラッシングでは取り除けません。
歯石が蓄積すると、歯の表面が黄ばみやすくなるだけでなく、口腔内の健康にも悪影響を及ぼします。
② 犬の歯の色素沈着
食べ物やおやつに含まれる色素が歯に付着することも、黄ばみの原因となり、狭義の意味ではこれがいわゆる『黄ばみ』になります。
特に、色の濃い食べ物やおやつは、歯の表面に色素が沈着しやすく、黄ばみが目立つようになります。
見分けるポイントは、
・歯全体が黄色い
・色がついている部分の縁がぼやけている
・凹凸がなく、表面は滑らか
高齢になるにしたがって、加齢の影響で歯が黄ばんでくることもあります。
また、歯の中(歯髄)で出血をした後、その赤色が生体で処理されると黄色みがかって見えるようになることもあります。
この場合は歯の中で深刻な状態が進んでいることも多く、なるべく早くレントゲンを撮って歯の中の状況を把握し、適切な治療をする必要があることが多いです。
③ 犬の歯のエナメル質の喪失
エナメル質は歯の表面を保護する滑らかな層で、身体の中でもっとも硬いとされ、骨や鉄よりも高い硬度を持ちます。
モース硬度:貴金属の硬さを10段階で表したもの
ダイヤモンド:10
エナメル質:7
骨・象牙質:5
鉄:4
爪2.5
ただ、非常に薄く、さまざまな原因でそれが取れたりなくなったりすることがあります。
・先天的なエナメル質形成不全
・加齢による生理的咬耗
・摩耗、外傷
・食事の影響(特に糖質過多な人間の食べ物)による酸の影響
エナメル質が薄くなると、内部の象牙質が透けて見えるようになります。象牙質は黄色っぽい色をしており、さらには歯石がつきやすいため、エナメル質の喪失によって歯が黄ばみます。
◆犬の歯の黄ばみから健康へ与える影響とは
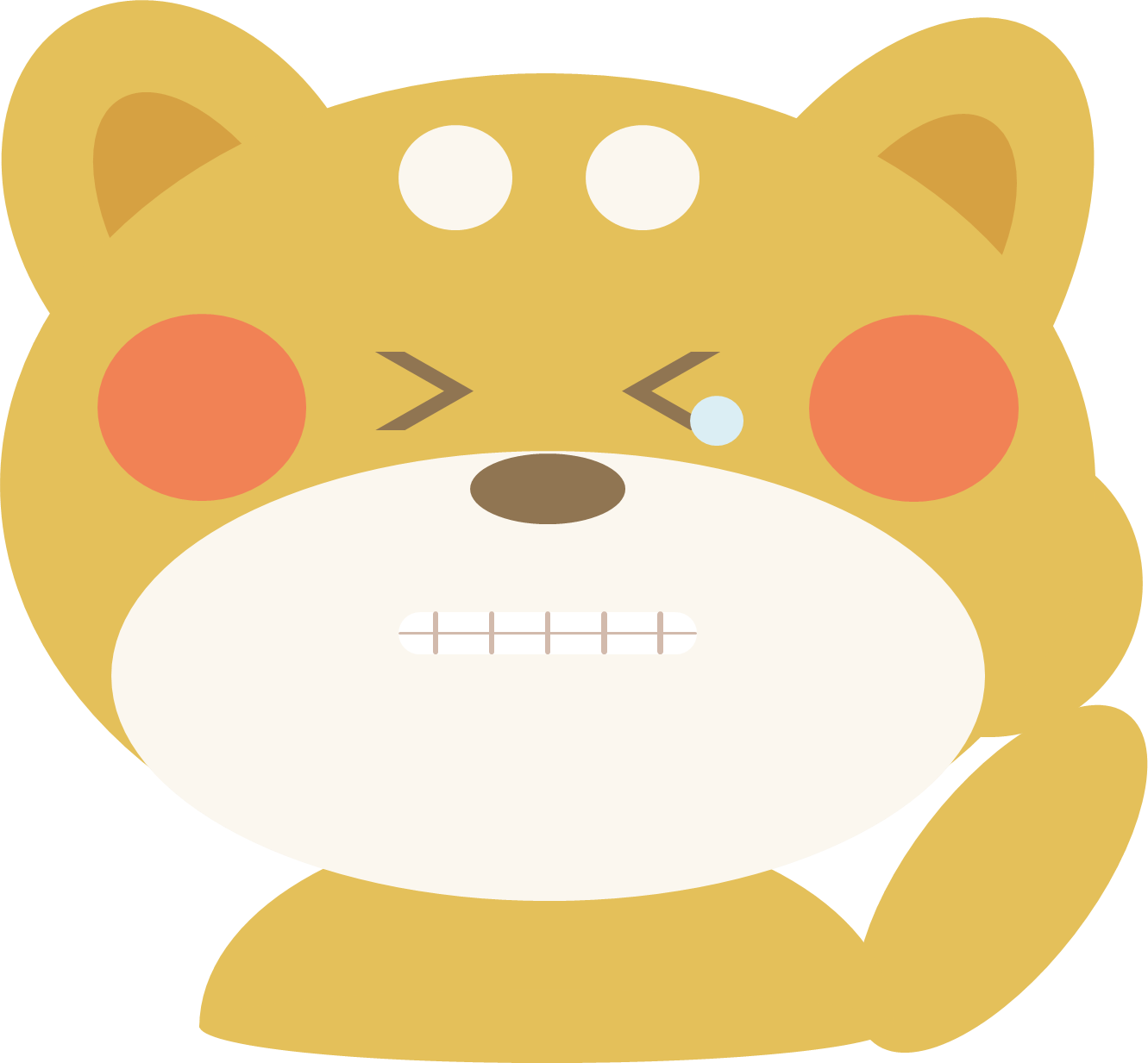
① 口臭の悪化
歯の黄ばみとともに口臭も悪化します。口腔内の細菌が増えると、悪臭を放つ化合物が生成されるためです。口臭は犬自身にとっても不快なものであり、飼い主との触れ合いにも影響を及ぼします。
② 歯周病のリスク
歯垢や歯石が蓄積すると、歯周病のリスクが高まります。歯周病は歯肉の炎症や出血、歯の動揺を引き起こし、最終的には歯が抜け落ちる原因となります。歯周病は痛みを伴い、犬の食欲や生活の質にも影響を与えます。
③ 歯の損傷や抜け落ち
エナメル質が喪失すると、歯が欠けたり折れたりしやすくなります。
歯内の出血による色の変化であっても、同じように歯の根っこ部分に異常があり、そのせいで抜けてしまうことがあります。
また、歯周病が進行すると、歯が自然に抜け落ちることもあります。これにより、食事が困難になり、栄養摂取にも影響を与えます。
④ 全身の健康への影響
口腔内の感染が全身に広がることもあります。例えば、口腔内の細菌が血流に乗って体内を巡り、心臓や腎臓に影響を与えることがあります。また『エナメル質形成不全』はさまざまな全身疾患や薬物の影響から出ていることもありますので、原因となる疾患がその他の症状を出すこともあります。
◆犬の歯の黄ばみの予防と生活習慣とは
① 日常的な歯磨き
毎日の歯磨きは、歯の黄ばみを防ぐ最も効果的な方法です。
犬用の歯ブラシを使い、優しくブラッシングしましょう。
初めての場合は、犬が嫌がらない範囲で少しずつ慣らしていくことが大切です。
アポロどうぶつ病院では、犬の歯磨きトレーニングのサポートも行っていますので、いつでもご相談ください。

② 食事とおやつの管理
歯の健康を保つためには、食事とおやつの選び方も重要です。
低糖質で歯に優しい食べ物を選び、歯垢が付きにくいおやつを与えるようにしましょう。
硬すぎるおやつは避け、適度な硬さのものを選ぶことが推奨されます。

③ 定期的な歯科検診と歯石除去
黄ばみの程度や原因をより詳しく知るために、定期的に動物病院で歯科検診を受けることが大切です。
少なくとも半年に一度の検診を目安にしましょう。
歯石が蓄積している場合は、動物病院での歯石除去が効果的です。
エナメル質が喪失している場合は、原因が解決できるものであれば解決します。
ただし、原因をなくしても一度喪失したエナメル質が再生することはありません。
この場合はエナメル質の喪失部分にレジンというプラスチックのような材質のものを貼り付けたり、埋め立てたりしてすることも可能です(歯冠修復処置)
これによりエナメル質の平坦化と象牙質の被覆をすることによって歯石の付着を減らし、歯周病の進行を遅らせたり止めたりする効果が期待できます。

④ 定期的な運動とストレス管理
割れたり剥がれたり、外的な要因でエナメル質に傷をつけないようにするには、大きく騒いだり過剰に物を噛むような習慣を避けることが大切です。
そのためにはストレスが少なく、適度な運動や外出の機会がある生活が重要です。
またおもちゃを噛む遊びが好きな子であっても、その他の遊びのバリエーションを増やしてあげることで、カム遊びの頻度を下げることができれば、エナメル質に傷がつくことを予防できます。
これにより、健康な歯を保ち、全身の健康状態を維持することができます。

⑤ 歯に良いおもちゃの選び方
犬の歯に良いおもちゃを選ぶことも重要です。
硬すぎるおもちゃや骨、ひづめ、ヒマラヤチーズは避け、適度な硬さのものを選びましょう。
適度な柔らかさがありながら、動物の歯牙ではなかなか噛みきったり壊したりしにくい化学繊維(化繊)のタオル地でできたものなどがおすすめです。
◆犬の歯の黄ばみを取る方法とは
◎自宅でできるケア方法
実は、いったんついてしまった黄ばみを自宅でのホームケアで取り除くのは難しいケースが多いです。
ですので、毎日の歯磨きで、黄ばみが付着しないようにしていくことがもっとも効果的と言えます。
まだ歯みがきトレーニングの途中、だったり、なかなか口を触らせてくれないなどの場合は、口腔内スプレーや歯磨きシートを使うことで、黄ばみの付着を軽減することができる場合もあります。
◎専門的なデンタルケア
動物病院での専門的なデンタルケアが通常もっとも効果的です。
定期的な歯石除去やプロのクリーニングを受けることで、歯の健康を長期間維持することができます。
また、黄ばみや歯石の予防だけでなく、普段見えない歯の内側など、さまざまな場所の異常をいち早く見つけることが可能になります。
◎歯磨き剤やおやつの活用
犬用の歯磨き剤やデンタルケア効果のあるおやつを活用することもおすすめです。
これらの製品は、歯垢や歯石の形成を抑える成分が含まれており、日常的なケアに役立つかもしれません。
◆まとめと今後のケアのポイント
◎歯の健康維持の重要性
犬の歯の健康は、全身の健康と密接に関連しています。
歯の黄ばみを放置すると、口腔内の問題が全身に影響を及ぼす可能性があります。
日常的なケアを怠らず、健康な歯を保ちましょう。
◎継続的なデンタルケアの推奨
毎日のデンタルケアを継続することが、犬の歯の健康を維持する鍵です。
歯磨きやデンタルケア用品を活用し、愛犬の口腔内を清潔に保ちましょう。

◎定期的な歯科検診と適切な治療
定期的な歯科検診を受け、必要な治療を行うことが重要です。
獣医師の指導のもと、適切なケアを継続することで、愛犬の健康を守ることができます。
愛犬の歯の健康について心配なことがありましたら、いつでもアポロどうぶつ病院にご相談ください。
状態を細かく診査し、飼い主様から丁寧にヒアリングすることで、黄ばみの原因を解明し、その子に最適な方法をご提案します。

当院では歯科の特別診療を実施しておりますので、歯の症状でお悩みの方はご相談ください。
また、マンツーマンでの歯磨きトレーニングも実施しておりますので、ぜひご検討ください。

